 ズーボ
ズーボ一人暮らし、始めたいけど不安だらけだぞ…料理も家事も苦手だし、お金の管理もできるか心配で…



ズーボ、その気持ちすごく分かるよ。私も同棲を始める前は同じように不安でいっぱいだった。でも今は、福祉サービスをフル活用して安定した生活を送れているんだ。



福祉サービス…?なんだか難しそうだな…



大丈夫!難しくないよ。むしろ、これを知らないまま一人暮らしを始めるのは本当にもったいない。私の失敗談と成功体験を全部話すから、参考にしてね。
【この記事を読んでほしい人】
✅ ASDの特性があり、一人暮らしに不安を感じている
✅ 家事や金銭管理が苦手で、自立できるか心配
✅ 福祉サービスって何があるのか分からない
✅ 支援を頼ることに抵抗がある
✅ 実際の当事者の体験談を知りたい
この記事では、ASD当事者である私が、同棲生活で培った自立の知恵と、福祉サービスを徹底活用して安定した生活を送れるようになった具体的な方法を、すべてお話しします。
1. ASDの一人暮らしで直面しやすい3つの壁とその根本的な対策



まずは、ASDの特性を持つ私たちが一人暮らしで直面しやすい「壁」について、正直に話していくね。
壁①:「実行機能の障害」による家事・生活管理の困難
ASDの特性の一つに「実行機能の障害」があります。これは簡単に言うと、物事を計画的に進めたり、複数のタスクを同時にこなしたりするのが苦手という特性です。
具体的にはこんな困りごと:
- 料理の段取りが組めず、同時進行ができない
- 掃除や洗濯のタイミングが分からず、部屋が荒れる
- やるべきことの優先順位がつけられない
- 「あれもこれも」と思っているうちに何も進まない



うわー、全部当てはまるぞ…



大丈夫、これは気合が足りないとか怠けてるわけじゃなくて、脳の特性なんだよ。だから、特性に合った工夫とサポートが必要なんだ。
壁②:「感覚過敏」による環境への適応困難
ASDの人の多くが持つ「感覚過敏」は、一人暮らしにおいて意外と大きな壁になります。
よくある困りごと:
- 隣の部屋の生活音が気になって眠れない
- 照明の明るさや色が合わないとストレスを感じる
- 食材の匂いや食感が気になって料理が苦痛
- 外出先での刺激で疲れ果てて帰宅後動けなくなる
壁③:「予測困難」による金銭管理・計画立案の難しさ
将来を予測したり、長期的な計画を立てたりすることの難しさも、ASDの特性の一つです。
具体的には:
- 今月いくら使えるのか計算できない
- 「これくらいなら大丈夫」が積み重なって破綻する
- 突発的な出費に対応できない
- クレジットカードで使いすぎてしまう



これらの壁、私も全部経験したよ。でも今は、ちゃんと対策を立てて乗り越えられているんだ。次のセクションで具体的な方法を話していくね。
2. 【実録:私の場合】食事・家事・金銭管理の「壁」をこう乗り越えた!
食事問題の解決策:おうちコープ × 居宅介護の最強コンボ
問題だったこと:
- スーパーに行くだけで疲れ果てる(感覚過敏)
- 何を買えばいいか分からず、同じものばかり買ってしまう
- 料理の段取りが組めず、結局カップ麺やコンビニ弁当に…
私の解決策:おうちコープの宅配サービス
私は『おうちコープ』という生協の宅配サービスを利用しています。これが本当に生活を変えてくれました。
おうちコープのここが助かる:
- 週に一度、自宅まで食材を届けてくれる
- スーパーに行く必要がないので、感覚過敏による疲労が激減
- カタログを見ながらゆっくり選べる(店内のガヤガヤした環境が苦手な私には最適)
- 特に冷凍食品が充実しているのがポイント



冷凍食品を推す理由はね、保存がきくから「今日料理する気力がない…」という日も安心なんだ。賞味期限のプレッシャーがないって、ASDの私たちにとってすごく大事なことだよ。
さらに重要:居宅介護(家事援助)の利用
でも、宅配だけでは料理の問題は解決しません。そこで私が利用しているのが『居宅介護(家事援助)』という福祉サービスです。
私の利用状況:
- 週に一度、ヘルパーさんに来てもらっている
- 3〜5品の料理を作り置きしてもらう
- 一緒に料理をしながら、段取りや調理のコツも教えてもらえる



え、料理を作ってもらえるサービスがあるのか!?



そうなんだ!これは障害者手帳を持っている人が利用できる公的サービスで、費用も自己負担は1割程度。これがあるから、栄養バランスの取れた食事ができているんだよ。
作り置きのメリット:
- 疲れて帰ってきた日も、温めるだけで食べられる
- 栄養バランスが整う
- 「料理しなきゃ…」というプレッシャーから解放される
- 少しずつ料理の基本も学べる
【重要】居宅介護サービスを受けるための手続き



ただし、居宅介護サービスは申し込めばすぐ使えるわけじゃないんだ。いくつか手続きが必要だから、そこは知っておいてね。
必要な手続き:
- 区役所(市役所)の障害福祉課に相談
- 区分認定調査を受ける(調査員が自宅に来て、日常生活の困りごとを聞き取り)
- 審査会で障害支援区分が決定
- 受給者証の交付
- サービス事業所と契約
人によって受けられる支援内容が異なる
ここで大切なのは、受けられる家事援助の内容は、人によって違うということです。
私の場合は週1回の調理サポートを受けていますが、別の人は掃除や洗濯のサポートを受けていたり、頻度も週2回だったりと様々です。



だから、区役所の担当者や相談支援員とよく相談して、「自分にとって本当に必要な支援は何か」をしっかり伝えることが大切なんだ。
金銭管理の解決策:徹底した現金主義
問題だったこと:
- クレジットカードで「見えないお金」を使いすぎてしまう
- 今月いくら使ったか把握できない
- 気づいたら口座残高がピンチに…
私の解決策:クレジットカードは持たない
これは思い切った決断でしたが、私にとっては最も効果的な方法でした。
現金主義のメリット:
- 使ったお金が視覚的に分かる
- 財布の中身を見れば、残りいくら使えるか一目瞭然
- 「使いすぎ」を物理的に防げる
- 衝動買いのブレーキになる



ASDの特性として、抽象的な概念(クレジットカードの請求額など)より、目に見える具体的なもの(現金)の方が理解しやすいんだ。だから私は思い切って現金主義を徹底したよ。
具体的な管理方法:
- 月初めに、一ヶ月分の生活費を引き出す
- 週ごとに封筒に分けて管理
- その週の封筒の中身だけで生活する
- 余ったお金は「ご褒美貯金」へ



なるほど!シンプルだけど確実な方法なんだな。


3. 一人暮らしを始める前に!「住まい」と「心の準備」



食事や金銭管理の工夫も大事だけど、その前に「住まい選び」が超重要なんだ。ここを間違えると、すべてが崩れてしまうから。
住まい選びで重視すべき2つのポイント:「家賃」と「環境」



住まい選びって、何を基準にすればいいんだ?
多くの人は物件を選ぶとき、「おしゃれな部屋」「新築」などの見た目を重視しがちです。
でも、ASDの特性を持つ私たちにとって最も重要なのは、「無理なく払い続けられる家賃」と「自分の特性に合った環境」の2つです。
①家賃の安定が最重要な理由:
- 仕事が続けられなくなるリスクがある(過集中、感覚過敏による疲労など)
- 収入が不安定になる可能性を考慮すべき
- 家賃のプレッシャーがストレスになると、すべての生活が崩れる
- 「住む場所」は最も基本的な安全基地
②環境も同じくらい重要:
- 周辺の騒音レベル(幹線道路沿い、繁華街は避ける)
- 建物の防音性(木造より鉄筋コンクリートの方が音が気にならない)
- 日当たりや照明(自然光の入り方で気分が大きく変わる)
- 最寄り駅やスーパーまでの距離(疲れやすい私たちには重要)



私も最初は「せっかくの一人暮らしだし、素敵な部屋に…」と思ったけど、相談支援員さんに「まずは家賃の安定と環境を優先して」とアドバイスされて、本当に良かったと思ってる。
内見は絶対に行くべき!
ネットの写真だけで決めるのは絶対にNGです。
内見で確認すべきポイント:
- 実際に部屋にいて、落ち着けるかどうか
- 隣や上下階の生活音が聞こえないか(可能なら昼と夜、両方の時間帯で確認)
- 照明の明るさ、窓からの光の入り方
- 周辺環境の騒音(駅や道路からの距離、近隣施設)
- 収納の使いやすさ



確かに、環境が合わないと毎日ストレスになるもんな…



そうなんだ。だから、多少時間がかかっても、納得できるまで内見することをお勧めするよ。「ここなら落ち着いて暮らせそう」と感じられる場所を見つけることが大切なんだ。
私が利用している「セーフティーネット住宅」
ここで知ってほしいのが『セーフティネット住宅』という制度です。
セーフティネット住宅とは:
- 住宅確保要配慮者(障害者、高齢者、低所得者など)向けの登録住宅
- 家賃補助が受けられる場合がある
- 入居審査が柔軟
私の場合:
- セーフティーネット住宅に入居
- 家賃の約半分を自治体から援助してもらっている
- これにより、障害年金と少しのアルバイト収入で安定した生活が可能に



家賃の半分も援助してもらえるのか!?知らなかったぞ!
【重要】セーフティーネット住宅の現実



ただし、セーフティーネット住宅は「申し込めば誰でも利用できる」わけじゃないんだ。正直に言うと、結構大変な部分もあるよ。
利用するための条件:
- 住宅確保要配慮者であること(障害者手帳を持っているなど)
- 一定の所得基準を満たすこと(自治体によって異なる)
- 家賃補助を受けるには、別途審査が必要
手続きの大変さ:
- 申請書類が多い(所得証明、障害者手帳のコピー、診断書など)
- 審査に時間がかかる(数週間〜1ヶ月以上)
- 審査に通らない可能性もある
- 自治体によって制度の内容が異なる



私も申請から入居まで、約2ヶ月かかったんだ。書類を揃えるのも、何度も役所に足を運ぶのも大変だった。でも、それだけの価値はあったよ。
セーフティーネット住宅の探し方・相談先:
- 各自治体の住宅課に相談
- セーフティネット住宅情報提供システムで検索
- 相談支援事業所に相談(後述)
- 障害者相談支援センターに相談



手続きは大変そうだけど、家賃が半分になるなら挑戦する価値はあるな!
心の準備:完璧を目指さない
一人暮らしを始める前に、もう一つ大切な「心の準備」があります。
それは、「完璧な自立」を目指さないことです。
私が学んだこと:
- 料理ができなくても、宅配と作り置きがあればOK
- 掃除が苦手でも、最低限のルーティンがあれば大丈夫
- お金の管理が完璧じゃなくても、仕組みでカバーできる
- 支援を頼ることは、弱さではなく賢い選択



「一人でなんでもできなきゃ」と思っていた頃は本当に苦しかった。でも「使える支援は全部使おう」と割り切ってから、すごく楽になったんだ。
4. 【最重要】安定した自立生活を支える「福祉サービス」徹底活用ガイド



福祉サービスって、具体的にどんなものがあるんだ?



ここが一番伝えたいところ!私が実際に利用しているサービスを全部紹介するね。正直、これらのサービスなしでは自立生活は不可能だったと思う。
最初に検討してほしい:「計画相談支援」
これは声を大にして言いたい。計画相談支援を、もっと早く利用すればよかったと、心から後悔しています。



だから、一人暮らしを考えている人には、ぜひ計画相談支援の利用をお勧めしたいんだ。
計画相談支援とは:
- 福祉サービスの利用計画を一緒に立ててくれる専門家
- どんなサービスが使えるか教えてくれる
- 申請の手続きをサポートしてくれる
- 定期的に状況を確認し、プランを見直してくれる
計画相談を使わなかった時の私:
- どんなサービスがあるか分からず、情報収集だけで疲弊
- 申請書類の書き方が分からず、何度も役所に行く羽目に
- 結局、使える支援を見逃していた
計画相談を使い始めてから:
- 「あなたの場合、このサービスが使えますよ」と具体的に教えてもらえた
- 申請書類も一緒に作成してくれた
- 定期的な面談で、困りごとを相談できる安心感
- サービスのコーディネート役として、すべての支援をつなげてくれた



なるほど、福祉サービスの「案内役」みたいな存在なんだな!



そう!本当に頼りになるんだ。計画相談支援は基本的に無料(自治体による)だから、利用を検討してみてほしい。もちろん、自分で情報を集めて申請できる人もいるけど、私にとっては本当に助かるサービスだったよ。
計画相談支援の利用方法:
- 市区町村の障害福祉課に相談
- 相談支援事業所を紹介してもらう
- 相談支援専門員との面談
- サービス等利用計画案の作成
- 各種福祉サービスの申請・利用開始
私が実際に利用している福祉サービス一覧
①居宅介護(家事援助)
すでに食事のところで触れましたが、改めて詳しく説明します。
サービス内容:
- 調理、掃除、洗濯などの家事援助
- 買い物の同行支援
- 服薬管理のサポート
私の利用状況:
- 週1回、2時間程度
- 主に調理の作り置きをお願いしている
- 自己負担:1回あたり約300円程度(所得により異なる)
申請に必要なもの:
- 障害者手帳(精神・療育・身体のいずれか)
- 医師の意見書
- サービス等利用計画案(計画相談で作成)
- 区分認定調査の受診
参考:厚生労働省「障害福祉サービスについて」
②就労移行支援
就労移行支援とは:
- 一般企業への就職を目指す障害者向けの訓練・支援サービス
- ビジネスマナー、PCスキル、コミュニケーションスキルなどを学べる
- 就職活動のサポート、就職後の定着支援も
私の経験:
- 約1年間通所
- 自分の特性に合った働き方を見つけられた
- 時間管理、報告・連絡・相談の練習ができた
- 「過集中」の制御方法も、ここで学んだ





就労移行支援では、単に就職するためのスキルだけじゃなく、「自分の特性との付き合い方」も学べたのが大きかったよ。
③障害者手帳
障害者手帳の種類:
- 精神障害者保健福祉手帳(ASDの場合は主にこちら)
- 療育手帳(知的障害を伴う場合)
- 身体障害者手帳
手帳を持つメリット:
- 各種福祉サービスの利用が可能に
- 税金の控除・減免
- 公共交通機関の割引
- 医療費の助成(自治体による)
- 障害者雇用での就職も選択肢に
私が実感している手帳のメリット:
- 居宅介護サービスが利用できる
- 映画館や美術館の割引
- 通院時のバス代が半額
申請方法:
- かかりつけの精神科・心療内科で診断書を作成してもらう
- 市区町村の障害福祉課に申請
- 審査後、手帳が交付(約2〜3ヶ月)
④障害年金



障害年金…?年金って、高齢者がもらうものじゃないのか?



それは「老齢年金」だね。「障害年金」は、障害によって働くことが困難な人が受給できる年金なんだ。年齢は関係ないよ。
障害年金とは:
- 病気やケガで生活・仕事に制限がある人が受給できる
- ASDも対象になる
- 障害の程度により、1級・2級・3級に分かれる
私の場合:
- 障害基礎年金2級を受給
- 月額約6.5万円(2024年度の金額)
- これが生活の基盤になっている
障害年金のここが重要:
- 収入の安定基盤ができる
- 働けない・働きづらい期間があっても生活できる
- 精神的な安心感が得られる



正直、障害年金がなかったら、今の安定した生活は不可能だったと思う。これは本当に重要な制度だよ。
申請のポイント:
- 初診日から1年6ヶ月経過している必要がある
- 医師の診断書が必須
- 社会保険労務士に相談するのがおすすめ(障害年金専門の社労士がいる)
- 申請は難しいが、諦めずにチャレンジしてほしい
参考:日本年金機構「障害年金」
福祉サービス利用の心構え
①支援を頼ることは恥ずかしいことじゃない
これが一番伝えたいことです。
私も最初は「人に頼るなんて…」「自分でなんとかしなきゃ…」と思っていました。
でも今ははっきり言えます。支援を頼ることは、自立するための賢い戦略です。
②情報は自分から取りに行く
残念ながら、福祉サービスは「自動的に」は提供されません。
自分で情報を集め、申請しないと利用できないのです。
だからこそ、計画相談支援のような「案内役」の存在が重要なんです。
③一度断られても諦めない
福祉サービスの申請は、正直、スムーズにいかないこともあります。
書類の不備、審査に時間がかかる、一度は却下される…など。
でも、諦めないでください。相談支援員や社労士の力を借りて、再チャレンジしましょう。
5. ASD特性を活かす!生活を助ける便利グッズ・アプリ



福祉サービス以外にも、日常生活を助けてくれるものってあるのか?



あるある!特にアプリは本当に便利だよ。私が実際に使っているものを紹介するね。
料理アプリ:DELISH KITCHEN
なぜDELISH KITCHENが良いのか:
ASDの特性の一つに「視覚優位」があります。文字で書かれたレシピより、動画で見る方が圧倒的に理解しやすいのです。
DELISH KITCHENのここが助かる:
- 動画で手順が見られる(視覚優位な特性に合致)
- 一つ一つの工程が明確
- 「次は何をするか」が直感的に分かる
- レシピを見ながら、動画を一時停止して作業できる



「玉ねぎをみじん切りにする」と文字で書かれても、どのくらいの大きさか分からなかったんだ。でも動画なら一目瞭然!これは本当に助かってる。
その他の便利アプリ・ツール
①タイマーアプリ(過集中防止)
- 作業時間を区切る
- 休憩のリマインダー
- 過集中の暴走を防ぐ


②家計簿アプリ(シンプルなもの)
- 現金管理と併用
- 何にいくら使ったか記録
- グラフで可視化されると分かりやすい
③ToDoリストアプリ
- やるべきことを視覚化
- 完了したらチェック
- 達成感が得られる
④ノイズキャンセリングイヤホン
- 感覚過敏対策
- 外出時の疲労軽減
- 集中したい時にも



アプリやツールは、自分の特性に合ったものを選ぶのがポイント。無理に複雑なものを使おうとしなくていいんだよ。
6. まとめ:支援を頼ることは、一人暮らしを成功させるための「戦略」だ



ズーボ、どうだった?一人暮らし、少しイメージできた?



ああ!思ってたより使える支援がたくさんあるんだな。まずは計画相談から始めてみるぞ!
最後に、この記事でお伝えしたかった大切なポイントを3つだけ、おさらいします。
POINT
✅ ASDの特性による困難は「工夫」と「福祉サービス」で乗り越えられる
✅ 計画相談支援の利用を検討し、使えるサービスを全て把握する
✅ 支援を頼ることは弱さではなく「自立のための戦略」である
私が実際に利用しているサービス:
Tips
- おうちコープ(食材宅配)
- 居宅介護(週1回の家事援助)
- セーフティネット住宅(家賃補助)
- 計画相談支援
- 就労移行支援
- 障害者手帳
- 障害年金
これらのサービスがなければ、私の自立生活は不可能だったと断言できます。
一人暮らしを始めようとしているあなたへ。
完璧な自立を目指す必要はありません。
使える支援は全部使って、あなたらしい生活を築いてください。
支援を頼ることは、恥ずかしいことでも弱いことでもありません。
それは、自分の特性を理解し、戦略的に生きるということです。
この記事が、あなたの一歩を踏み出す勇気になれば幸いです。
あなたの新しい生活が、安定した充実したものになりますように。
更新履歴
- 第1稿投稿 2025年10月29日(記事コンテンツアップ)
参考資料・引用元
- 厚生労働省「障害福祉サービスについて」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/index.html
- 日本年金機構「障害年金」 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/index.html
- セーフティネット住宅情報提供システム https://www.safetynet-jutaku.jp/
- おうちコープ https://www.ouchi.coop/
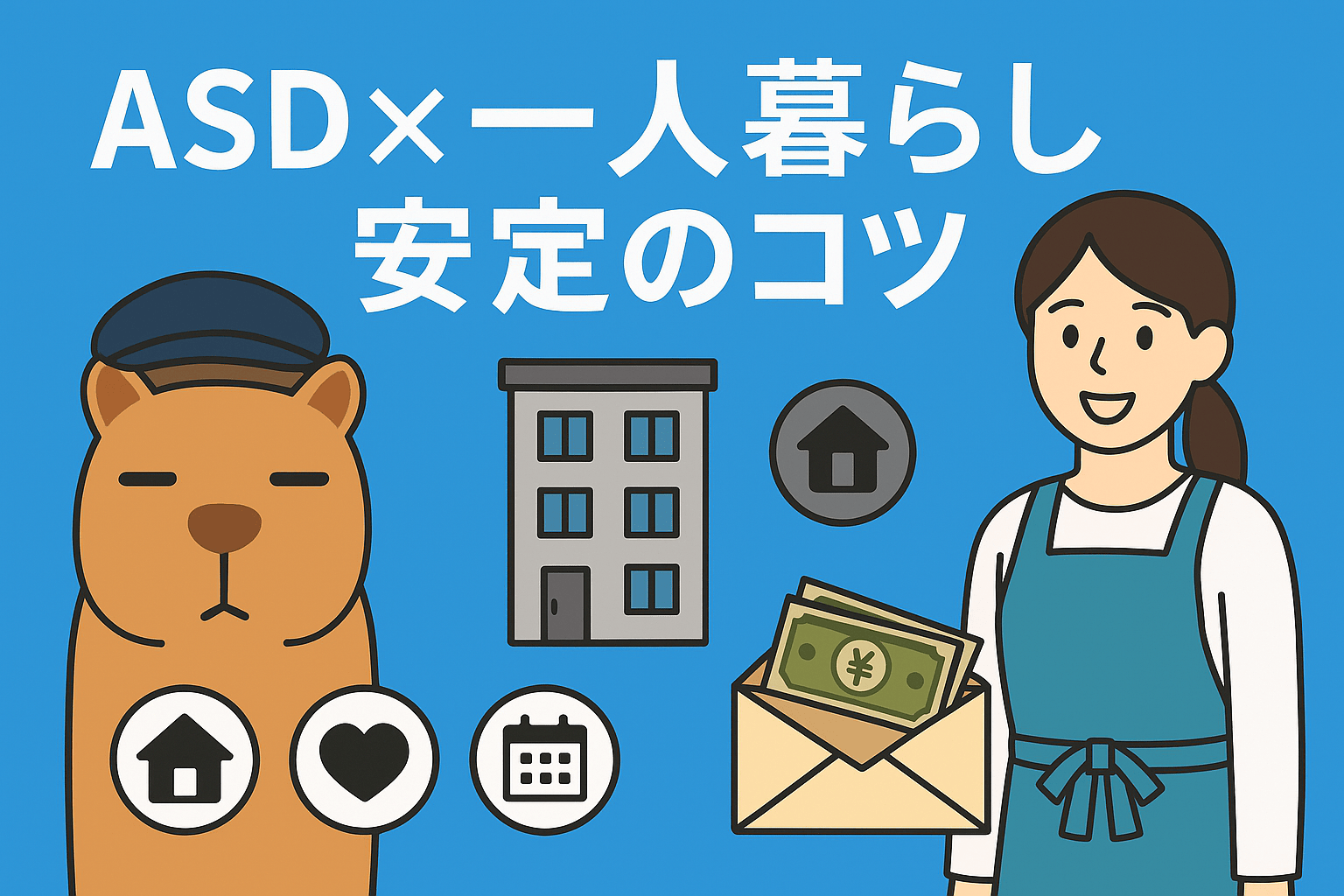
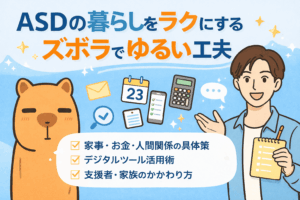
コメント